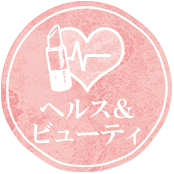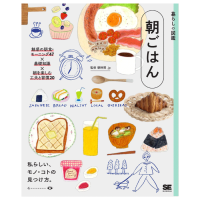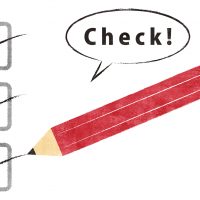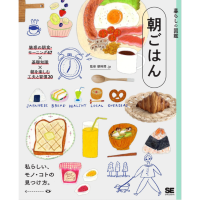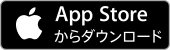| ■ 黄体期には眠気が強くなる | ||||||
|
女性の体は思春期に入ると初潮を迎え、成熟していきますが、こういった変化は主に、エストロゲンとプロゲステロンというふたつの女性ホルモンによるものです。このホルモンは下記のような働きをしますが、内分泌のリズムは睡眠のリズムと相関しているといわれ、睡眠状態はホルモンで変化し、性差、年齢、月経周期によっても変化すると考えられます。
生理から排卵まで(卵胞期)はエストロゲンの分泌が増え、体(お肌も)も心も眠りも安定します。しかし、排卵を境に、生理がくるまでの間(黄体期)はプロゲステロンの分泌が増え、その変動で体調が不安定に。
|
|
|||||
|
実はプロゲステロンには睡眠作用があるといわれ、黄体期や妊娠初期は眠くなることが多いようです。黄体期は基礎体温が高くなるため、夜になっても深部体温(直腸の体温<内臓の体温で、人は深部体温が高いと眠りにくく、低くなると眠りやすくなる性質がある>)が十分に下がらず、寝つきにくくなったり、夜間の眠りの質も低下しやすくなります。プロゲステロンの影響で体調や気分も不安定になるために、さらに日中、眠気が強くなったり、やる気がでないといった状態になりやすいようです。
エストロゲン(卵胞ホルモン)
プロゲステロン(黄体ホルモン)
|
|
||||||||||
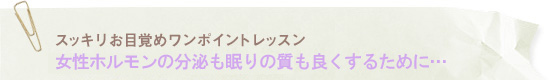 |
|
・規則正しい生活を心がける
睡眠のリズムを正し、ホルモン分泌のリズムを正常にするためには、寝起きする時間はなるべく一定に。また、深部体温の温度を下げたほうが眠りやすいといっても、それは体を冷やせば良いということではなく、「冷えを改善して、寒い夜もぐっすり眠ろう」でご紹介したように、全身の血行をよくして放熱を促すのが正解。昔からお腹を冷やすと健康によくないといわれる通り、内臓の体温が1℃下がると消化力も免疫力も大幅に低下するといわれています。カンジタ膣炎なども免疫力が低下したときに起こりやすくなるので、絶対にお腹は冷やさないこと。寝つきが悪いときはぬるめのお風呂にゆったり入り、放熱を促しましょう。また、ストレスは自律神経の働きを乱し、眠りを妨げる原因になるので、リラックスを心がけましょう。
参考図書/「睡眠とメンタルヘルス」(ゆまに書房) 監修:上里一郎 編:白川修一郎
|
 |