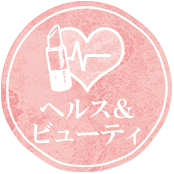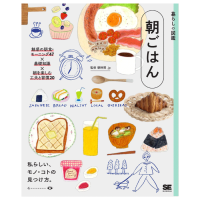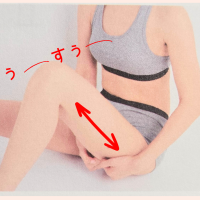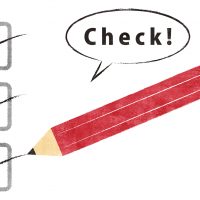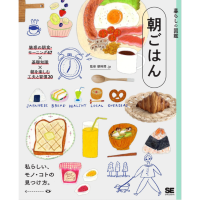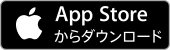朝起きても体が重い。ずっと眠いし、頭がぼんやり…。そんな“梅雨のだるさ”を感じていませんか?初夏の体調不良には、気圧や気温の変化による「自律神経の乱れ」だけでなく、体温のリズムの乱れや副腎機能の低下が関係していることも少なくありません。
私の治療院でもめまい・だるさ・むくみ・頭痛・PMS・睡眠の乱れなどの自律神経症状を訴える患者さんが増える季節です。

体温は朝が最も低く、夕方に向かって徐々に上昇する自然なサイクルがあります。この“体温リズム”は自律神経やホルモンとも密接に関係しており、崩れると倦怠感・冷え・胃腸トラブル・気分の落ち込みなど、さまざまな不調の引き金になります。
今回は、梅雨の季節を健やかに過ごすためのセルフケア習慣をご紹介します。
季節の変わり目に。自律神経と腸を整える5つのやさしい習慣

【体温リズムを整える5つの習慣】
【1】朝起きたらまず光を浴びる
自然光を浴びることは、体内時計をリセットするための大切な合図。朝の光を取り入れることで、気持ちを安定させるセロトニンが分泌され、自律神経やホルモンの働きが整いやすくなります。
【2】起きる時間を毎日そろえる
週末や休日に遅くまで寝ていると、平日の体温や月経リズムにもズレが生じやすくなります。毎日ほぼ同じ時間に起きることで、体のサイクルが整い、朝から軽やかにスタートしやすくなります。
【3】空腹時に甘いもの・炭水化物を控える
朝の空腹時にいきなりドーナツや菓子パンを食べると、血糖値が急上昇し、その反動で強い眠気やだるさを招くことがあります。食物繊維が入った温かいスープ、卵や豆類などのタンパク質が多い「おかず」を先に食べましょう。食後の血糖値の乱高下は副腎にストレスをかけるので要注意です。

【4】食後に10〜15分の軽いウォーキング
食後のウォーキングは、胃腸の消化を助け、血糖値の急な上昇を防ぐ効果があります。むくみの解消、肝ぞうのデトックスにもおすすめです。
【5】夕方はストレッチとおなかのケアを
夕方は体温が最も高まる時間帯。体を少し動かした後、「おなかのハンズケア」でおなかに手をあてて深呼吸をすると、自律神経と胃腸の働きが整います。夕方に体温がしっかり上がると、そのあとに体温が下がって夜間の深い眠りを促します。

【まとめ】
梅雨の不調は、気圧の変化や気温差に加えて、「体温リズム」や「副腎機能」の乱れが影響しています。朝の光、体温コントロール、血糖値を整える食べ方、そしておなかへのセルフケア。これらのやさしい習慣は、体に備わる自然な回復力を高めてくれ、副腎が元気になると胃腸の働きも良くなります。
季節の変化が大きい時期こそ、ご自身の体にそっと寄り添ってあげましょう。「おなかのハンズケア」と組み合わせた内側からのケアで、カラダとココロを整えてみませんか?

【2分でできる】おなかのハンズケア動画
自律神経の乱れ、おなかの冷えが気になる方に。優しくお腹に手を当てて行う簡単セルフケアで、おなかの働きをサポートします。
▼動画はInstagramでチェック
【梅雨のだるさに/回盲弁のハンズケア】
【おなかの冷えに/腸のハンズケア】
次回は「毎年、梅雨になると体がつらい…それ、腸からのサインかも?」を予定しています。お楽しみに!