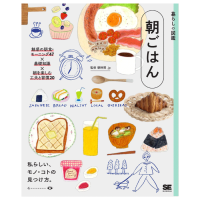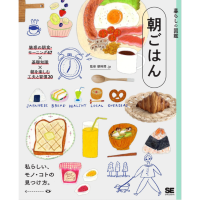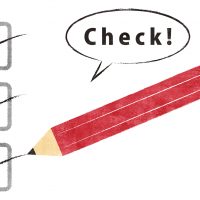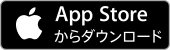6月16日:今日は「カビ取るデー」
ジメジメする梅雨はカビが増えやすい時期。こまめに掃除や換気をしてカビ予防を徹底したいものですね。
さて、今日は梅雨シーズンということで、梅雨の語源について調べてみました。
梅雨の語源とは?

気象庁の情報によると…「梅雨」と言う理由は、いくつかの説があるそうです。
まずは、中国で梅の実が熟す頃に降る雨なので「梅雨」と呼んでいたことが日本へ伝わったと言われています。
また、「カビ(黴)」がよく生える時期から「黴雨(ばいう)」と呼んだこと。そして、くさるという意味の「潰える(ついえる)」から変化したと言われていますよ。
はっきりとはしていませんが、上記が主な説なんですって。
ちなみにテレビで「梅雨入りしました」等のお知らせが報道されることがあると思います。この基準ってどこからきているのでしょうか?
地域によって梅雨入りの時期には差がありますが、「梅雨入り」はこれまでの天候とその先1週間の予報を元に、雨や曇りが多くなり始める時期を指しています。
そのため、具体的な「雨がこのくらい降ったら…」というような基準は特にないそうですよ。
(参考:気象庁|はれるんランド)
***
雨や湿気の影響で気持ちも下がりやすい梅雨シーズン。カラフルなレイングッズや室内での楽しみを増やして、乗り切っていきたいですね。
「カビ取るデー」とは?
洗濯槽クリーナー「カビトルネード」を販売する株式会社リベルタが制定。カビや汚れが気になる6月の梅雨の時期と、12月の大掃除の時期に記念日を制定することで、洗濯槽のカビをクリーナーを使ってきれいにすることはもとより、他のカビも取る意識を高めてもらうのが目的。日付は6月と12月の年2回、カビを「ト(10)ル(6)=取る」の語呂合わせで16日としたもの。